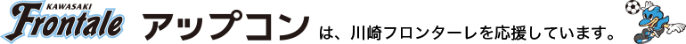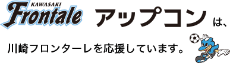土間コンクリート床のクラック(ひび割れ)の原因は?種類別の対処方法と注意点

今回は土間コンクリート床に生じるクラックの発生原因やクラックの種類、対処法、補修を依頼する際の注意点などについてご紹介していきます。
そもそもクラックとは「ひび割れ」や「亀裂」という意味で、建築物においてはコンクリートやモルタルなどに発生する細長いひび割れのことを指します。
このまま放置していても良いのか、それとも早急に補修すべきなのかなど、クラックへの対処の仕方で悩まれている方は、ぜひ参考にご覧ください。
目次
土間コンクリート床のクラックを放置すると?
土間コンクリート床のクラックを放置すると、見た目が損なわれるだけでなく、クラックから水などが浸透して割れ目が大きくなったり、コンクリート内の鉄筋が錆びて、床の強度が弱まったりする恐れがあります。倉庫や工場などでは、ひび割れにより車両やフォークリフト、AGV・AMRといったロボットの走行に支障が生じ、作業効率が低下することもあります。
さらにクラックが進行すると、構造的な問題を引き起こします。
そのため、コンクリート床のひび割れを見つけたら、軽微なものでも放置をせず早めの対処が望ましいと言えます。
土間コンクリート床にクラックが発生する原因

土間コンクリート床にクラックが生じる原因は複数あり、またいくつもの要因が重なり合っていることが通常です。ここではクラックの発生原因として一般的なものをご紹介していきます。
土間コンクリート床のクラック原因①:乾燥による収縮
土間コンクリートに生じるクラックの原因としてまず考えられるのが、乾燥による収縮です。
コンクリートは内部に水分を含んでおり、この水分が蒸発して体積が減少することで収縮が起こります。ですが、コンクリートを拘束している周囲の構造物などの部材は収縮をあまり起こさないので、引張力(外側に引っ張る力)が発生し、コンクリートにひび割れが発生するのです。
土間コンクリート床のクラック原因②:凍結と融解
冬の寒さが厳しい寒冷地などでは、コンクリートに含まれた水分が凍結と融解を繰り返してクラックが発生することがあります。
一度ひび割れが発生すると、そこから雨や水が再び浸入しやすくなり、侵入した水分が凍結と融解を繰り返すことで、ひび割れが徐々に拡大することも考えられます。
土間コンクリート床のクラック原因③:気温変化による膨張と収縮
気温変化による収縮も、土間コンクリート床にクラックが発生する主な原因の一つです。
コンクリートは高温になると膨張し、低温になると収縮する性質を持っています。この性質上、昼夜や季節の温度変化でコンクリートに膨張と収縮が繰り返し起こり、内部に応力が発生することでクラックが発生します。
ただ、気温変化によるコンクリートの膨張と収縮は避けられない現象のため、施工時の適切な材料の選定や、クラックを防ぐための対策がポイントとなります。
土間コンクリート床のクラック原因④:不同沈下や地盤沈下
土間コンクリート床のクラックの原因として、不同沈下や地盤沈下の発生も考えられます。
建物の一部が不均等に沈下することを不同沈下といい、不同沈下は地盤の強度や性質の違い、外部からの荷重の偏りなど、さまざまな原因で発生します。これがコンクリート床で発生すると、床に応力がかかり、クラックが発生します。
また、地盤が徐々に沈んでいく現象を地盤沈下といい、地盤沈下は主に地下水の過剰な汲み上げや地盤の圧密、地殻変動などによって発生します。地盤沈下が進行すると、床下に空隙(くうげき)や空洞ができ、その結果としてコンクリート床がたわんでストレスがかかり、クラックが生じます。
不同沈下と地盤沈下は、どちらも建物全体の安全性に関わる重大な問題ですので、クラックを補修するだけでなく、クラックの根本的な原因となっている不同沈下や地盤沈下に対して処置する必要がある点に注意が必要です。
土間コンクリート床のクラック原因⑤:中性化による膨張
土間コンクリート床のクラックの原因の一つに、中性化による膨張があります。
コンクリートはもともと強アルカリ性なのですが、空気中の二酸化炭素が侵入して化学反応を起こすことで中性に近づいていきます。中性化が進行するとコンクリート内部にある鉄筋が錆びて体積が膨張し、この膨張によって圧力がかかり、ひび割れが発生するのです。
中性化は経年劣化ですので完全に避けることは難しいですが、コンクリートの表面を保護したり、アルカリ性を維持するための中性化処理を行うことで、進行を遅らせることが可能です。
土間コンクリート床のクラック原因⑥:地震によるストレス
地震による揺れで土間コンクリート床に大きなストレスがかかり、クラックが生じることもあります。
地震が発生すると、土間コンクリート床は上下左右に激しく振動します。するとコンクリート内に大きな応力が発生し、この応力がコンクリートの強度を超えるとひびが入ってしまうのです。また、規模の大きな地震や継続時間が長い地震ほど被害が大きくなりやすいのはもちろんのこと、余震が続くと応力が繰り返し加わりますので、クラックが徐々に拡大する恐れがあります。
そのため、地震が落ち着いたからといって安心せず、迅速に点検と補修に取りかかることが望ましいと言えるでしょう。
土間コンクリート床のクラック原因⑦:設計や施工の影響
土間コンクリート床のクラックは、設計時に想定していない過度な荷重や、機械やフォークリフトなどの振動でも発生します。またコンクリートを打設する際、コンクリートが硬化する過程で水分が蒸発して体積が収縮し、クラックの発生につながるケースもあります。
これから打替えを検討されている方は、想定される荷重や使用状況を業者に伝えること、そして業者はこれらの条件を十分に考慮した荷重計算や施工管理を行うことが求められます。
土間コンクリート床に発生するクラックの種類と対処方法

クラックは進行度や深刻度によって対処方法が異なることから、状態によって大きく2種類に分類されます。この分類方法以外に発生原因別に呼び分ける場合もありますが、ここでは深刻度による分け方と対処方法をご紹介していきます。
クラックの種類①:ヘアークラック(深刻度の低いひび割れ)
土間コンクリート床に生じるクラックの一つが、ヘアークラックと呼ばれる髪の毛のように細い小さなひび割れです。乾燥による収縮や経年劣化などが原因で発生し、多くのコンクリート構造物で見られる一般的な現象となります。
具体的な目安としては、コンクリート表面に生じる幅0.3mm以下・深さ4mm以下のひび割れを指し、この程度のひび割れであれば建物の強度や構造的な問題には直結しにくいので、すぐに大規模な補修が必要となるわけではありません。
とは言え、危険度が高まる前に原因を突き止め、対処するのが望ましいため、原因の特定および補修を専門業者に依頼することをおすすめします。
クラックの種類②:構造クラック(深刻度の高いひび割れ)
コンクリートの表面に生じるヘアークラックに対して、内部まで達している恐れのある深くて幅の広いひび割れを構造クラックといいます。一般的に幅0.3mm以上・深さ4mm以上のひび割れを指しますが、中にはひび割れが貫通しているケースもあり、このようなクラックを貫通クラックと呼んでいます。
そして構造クラックは、不同沈下や地盤沈下、地震などの大きな地殻変動などもクラックの原因にもなるケースもあります。
構造クラックは、すでにコンクリート床の強度が低下しているケースや、放置することでひび割れから水が浸入した場合、内部にある鉄筋の錆びが進行するなどの影響が考えられます。さらに劣化が進行すると建物全体の構造的な安定性に悪影響を及ぼしかねません。
そのため、早急に専門業者に調査を依頼し、適切な補修を行う必要があります。
土間コンクリート床のクラックを補修する際の注意点
クラックが不同沈下や地盤沈下が原因で発生している場合、クラックだけを補修しても根本的な解決には至らず、再度クラックが生じる恐れがあります。床下の地盤沈下が進行し続けている可能性があるからです。
そのため、地盤沈下で生じるクラックの根本的な原因である床の沈下や、床下の空隙・空洞を解決してからクラックの補修を行うことをおすすめします。
弊社アップコンの沈下修正「アップコン工法」は、クラックの原因となっている床の沈下、床下の空隙・空洞充填を行う事で、地盤沈下が原因であるクラックの根本的な原因を解決します。
なお、沈下修正の工事内容についてはこちらの記事「【沈下修正の基礎知識】工事内容・工法・施工の流れなど」を参考にご覧ください。
沈下修正「アップコン工法」の特長
アップコン工法は沈下・段差・傾き・空隙・空洞が生じた既設コンクリート床下の地盤にウレタン樹脂を注入し、床下に注入されたウレタン樹脂が、短時間で発泡する圧力で地盤を圧密強化しながら、地耐力を向上させ、コンクリート床を下から押し上げて元のレベルに修正する工法です。
倉庫や工場といった土間コンクリート床に地盤沈下などが原因で生じたクラックの根本的な原因を解決します。
アップコン工法は既設のコンクリート床の取壊しをせず修正するため、機械や荷物を移動させる必要がありませんし、工期も最短1日(ウレタンの最終強度は約60分で発現)と、工場・倉庫・店舗などの操業や営業を止めずに施工が可能です。
クラックの進行や床の傾き、段差などにお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
詳しい施工の特長や施工の流れ、よくある質問等については「アップコン工法とは」をご覧ください。
“ウレタン” で課題を解決するアップコン株式会社

私たちアップコンは、ウレタン樹脂を使用して工場・倉庫・商業施設・一般住宅などの沈下修正をおこなうこと、道路・空港・港湾・学校・農業用水路などの公共インフラの長寿命化をおこなうことで暮らしやすい社会とストック型社会へ貢献します。
また、ウレタン樹脂の新規応用分野への研究開発に取り組むことで、自ら市場を創りながら事業を拡大していきます。
「アップコン工法に適合する内容かわからない」「具体的な費用や工期が知りたい」「ウレタンでこんな施工ができないか」など、ご質問がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 トップメッセージ
トップメッセージ アップコンについて
アップコンについて 企業情報
企業情報 資格保有状況・
資格保有状況・ コーポレート
コーポレート ISOへの取り組み
ISOへの取り組み 環境への取り組み
環境への取り組み 健康経営
健康経営 ブランド・
ブランド・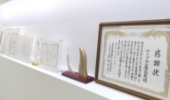 特許・受賞一覧
特許・受賞一覧 メディア紹介
メディア紹介 工場
工場 倉庫
倉庫 商業施設・店舗
商業施設・店舗 道路
道路 港湾
港湾 住宅
住宅